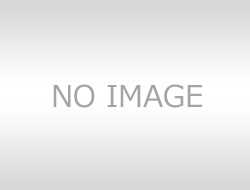私は現在、大阪の豊能町で高齢者傾聴ボランティアをさせていただいています。そこでお出会いしたのがデイサービスに来られていたHさん。ずっと親しくさせていただいていたが、まさかと思うことがありました。
何とわが養父市に、戦時中疎開されていたのです。疎開先は大屋町にある「山路寺」という真言宗のお寺。Hさんにとってその時の体験は忘れることのできない思い出のようでした。
お話を伺ううちにHさんの代わりに訪ねてみたくなりました。
そうこうしているうちに8月の終わり、関西養父市会の正垣さん、西川さん3人で訪れる機会を得ることができました。
当日新田光俊ご住職にお出迎えいただきました。祖父の時代のことであるにもかかわらず直筆の記録、写真、当時の事を記載された本など貴重な書類を用意して待っていて下さり、また美味しいお茶のおもてなしもあり感激しました。
当時、本堂の前の庭にはさつま芋を植え、規則正しい生活と今では考えられない厳しさと、しかし愛情に満ちた住職、先生、寮母さんに囲まれ、生活していたようです。その方たちは今はもう85歳になられています。懐かしいでしょうね。
大阪へ帰り早速Hさんにそのことを報告させていただきました。
冬の寒い日、お風呂で使ったタオルが朝、かちかちに凍りそのタオルで乾布摩擦をして背中がとても痛かったこと、親元からの荷物が待ち遠しかったこと、ゴマ塩が届き、外に積もった雪にかけた食べたこと、そんな楽しかった思い出が走馬灯のように駆け巡っているご様子です。
ただ、ある日送られてきた荷物の荷札の名前が、母親の名前になっている。不思議に思った。父が戦死していたのだ。それは悲しい思い出ではあったが、疎開者を快く受け入れた山路寺の住職夫妻に対する感謝の気持ち、そして大屋が第二の心のふるさとと思われていることを、思い出話の中にひしひしと感じた。
当時、養父市にこんな温もりのあるお寺があったのだと嬉しくなった旅であった。